はじめに:吃音に悩む親子に、まず届けたい言葉
吃音(きつおん)は、
本人にとっても、家族にとっても、“見えにくく、伝わりにくい悩み”を抱えやすいもの。
私自身も、小学4年生の吃音のある長男を育てながら、
どう声をかけたらいいのか、どう支えたらいいのか、たくさん悩んできました。
そんな中で、本は大きな心の支えになってくれました。
今回は、「吃音の子を育てる親」として、
本当に読んでよかった!と思えるおすすめの本を5冊、ご紹介します。
吃音に向き合う親子にとって、少しでもヒントや安心につながればうれしいです。
吃音と向き合う力をくれる5冊の本
1. 『「吃音」の正しい理解と啓発のために~キラキラを胸に』著:堅田 利明
ある日突然、言葉がつまるようになり、思うように話せなくなってしまった我が子💦
何が起きているのか分からず、私は不安でいっぱいになり、ただただ「どうしたらいいの?」と毎日ネットで情報を探し続ける日々。そんな中で、初めて「吃音」という言葉をしっかりと知り、初めて吃音の本として出会ったのが、この1冊です。
本書は、吃音のある子どもたち、そのご家族、教育現場の先生、言語聴覚士の方々など、さまざまな立場の方の声が集められた手記をまとめた1冊となっています。
読んでいく中で、「こんなにもたくさんの人が、同じような悩みを抱えているんだ」と知ることができ、
ひとりじゃないという安心感と、同時に“子どもを支えるためにできること”のヒントをもらえました。
吃音の支援は家庭だけでなく、教育現場や医療の分野にも関わってくることを知った1冊です。まさに“吃音を初めて知る人”にも寄り添った構成になっています。
何より、母として迷ってばかりだった私に、「まずは知ること、そしてできることから始めてみよう」と背中を押してくれた本でもあります。
落ち込む毎日で笑顔も消えていた私でしたが、この1冊があったからこそ、前向きな気持ちで息子と向き合っていこうと思えました。あの頃の私に勇気を与えてくれた1冊でもあります。
2. 『保護者の声に寄り添い、学ぶ 吃音のある子どもと家族の支援:暮らしから社会へつなげるために』著:堅田 利明 菊池 良和
長年にわたり吃音支援に携わってきた著者による、実践的な1冊です。
本書は、保護者がもっとも悩む「支援の方法」について、丁寧に、そして具体的に書かれています。
共著者の菊池良和先生は吃音の専門医であり、ご自身も吃音当事者のひとりです。その視点から語られる内容には、深い共感と信頼を感じました。
「保護者ができることをやっていこう」と言われても、「実際にはどうしたらいいの?」と戸惑うことは、私自身にも多々ありました。
簡単に言うけれど、どんな言葉で伝えればいいのか…考えるだけでなかなか行動に移せずにいたのです。
この本では、そんなときに役立つ「伝え方の手順」が、理由や効果、具体的なフレーズとともに紹介されています。
実際にどう伝えるか、どんな順序で話せばいいのかが明確に書かれていて、とても助けられました。
正直、「このまま伝えればいいや」と思って、本書を“カンペ”代わりに持っていったこともあるくらいです(笑)
そして今では、この本を担任の先生に1冊ずつお渡しし、毎年引き継いで読んでもらっています。保護者と先生が共に理解を深めていくための、大切な一冊になっています。
3. 『こどもの吃音症状を悪化させないためにできること ―具体的な支援の実践例と解説』編著者 堅田 利明
こちらも、言語聴覚士である堅田利明先生の著書です。
私の息子は現在小学4年生で、吃音の症状は今も続いています。この本は、まさにタイトルの通り「症状を悪化させないためにできること」がとても丁寧に、そして具体的に書かれています。
構成は「解説編」「実践編」「資料編」の三部構成になっており、特に実践編では、言語聴覚士の先生や保護者の方々の実際のエピソードが数多く紹介されています。
これらのエピソードは単なる感想ではなく、会話形式でリアルなやりとりが描かれているため、イメージしやすく、我が家のケースに置き換えて考えるのにもとても役立ちました。
また、子どもたち自身の素直な気持ちが綴られている場面もあり、親として「ハッ」とさせられる気づきも多くありました。
各エピソードには堅田先生による解説も添えられており、支援のポイントをより深く理解することができます。
4. 『キラキラ どもる子どもの物語』著:堅田 利明
こちらも堅田先生の本です。
本書は物語形式で語られており、吃音がある子どもの気持ちや、周囲の大人の関わり方がやさしく描かれています。難しい理論ではなく、実際の子どもたちの姿や思いに寄り添って書かれているため、自然と心に入ってくる内容でした。
読み進めるうちに、「あ、うちの子もこう感じているのかもしれない」と、これまで見えていなかった子どもの心の奥に少し触れられたような気がしました。
また、保護者としてどう向き合えばいいのか、自分が子どもにどんな言葉をかけてきたかを振り返るきっかけにもなりました。
「正しい知識を持つこと」「子どもの感じていることに目を向けること」の大切さを教えてくれる1冊です。
この本との出会いから、吃音について学ぶ道が始まりました。そして今も、その一歩一歩が、子どもと共に歩む大切な道のりになっています。
5. 『僕は上手にしゃべれない』著:椎野 直弥
吃音についての本をいろいろ調べている中で出会った1冊です。
支援の方法や関わり方を学ぶ本とは少し違い、吃音を抱えた主人公自身の目線で描かれた物語であり、著者の椎野直弥さんご本人も吃音当事者です。
これまで読んできた支援書では、どう関わるか、どう伝えるかといった「大人目線」の視点が多かったのですが、
この本を読んで、「息子自身が吃音をどう受け止めているか」に目を向けることの大切さに気づかされました。
「何か別のアプローチで、吃音をもっと自然に、自分の一部として理解してもらえたらいいな」
そう思っていた時期に、この本に出会ったのです。
椎野さんの語る言葉はとても等身大で、吃音を否定せず、無理に前向きにとらえるわけでもなく、
でもしっかりと向き合おうとする姿に、強さと優しさを感じました。
子どもが自分自身の言葉で、少しずつ理解していくためのきっかけになる一冊です。
読む人によって、気づくことも、感じることもそれぞれ違うと思いますが、親として、そして子ども自身にとっても、大切な出会いになるかもしれません。
まとめ:正解がないからこそ、「知ること」が力になる
吃音は、見た目ではわかりにくく、誤解されやすいからこそ、
本人も親もとても孤独を感じやすいもの。
でも、知ること、学ぶことは、私たちに「大丈夫だよ」と寄り添ってくれる力になります。
本を通して誰かの言葉に出会い、「私たちだけじゃない」と感じられた瞬間、
心がふっと軽くなることがあります。
完璧な対応や言葉がけなんてなくても、
「知ろうとする姿勢」「一緒に悩む姿勢」そのものが、
子どもにとっての安心になると、私は思っています。
紹介した5冊は、どれも親として、そして1人の人間として、
吃音と向き合うヒントをくれる本ばかりです。
もし気になる本があれば、ぜひ手にとってみてくださいね。

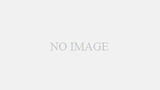
コメント