【はじめに】新学年、先生との最初の一歩
新学年が始まり、クラス替えや担任の先生との出会いに、ドキドキする季節。
小4の長男には、吃音があります。
普段は元気いっぱいでも、ことばが詰まることで戸惑いや誤解が生まれることも…。
だからこそ、新しい担任の先生には最初に伝えておきたいことがあります。
【伝えたいこと】吃音の子が安心して過ごすために
吃音は、目に見えにくいけれど、本人にとってはとても大きな「壁」になることがあります。
うちの子も、発表や音読、点呼のときに言葉が詰まりやすくなります。
でも、吃音=話せない、というわけではなく、話したいことはたくさんあります。
ゆっくり待ってもらえれば、ちゃんと自分の言葉で話すことができます。
だから担任の先生には、毎年、始業式の日に以下のようなことをお願いしています。
ここで注意ですが、先生も忙しい時期。息子のときも実際にあったのですが、
新規採用、先生1年目という方もいらっしゃいました。
一度にたくさんのことをお願いすると先生の負担にもなり、またどれもあやふやな対応になってしまい、
こんなはずじゃなかった…っとなってしまう場合もあります。
クラスの状況や我が子の様子をみながら、徐々に伝えていけばOKなので、
新学期は最低限、これだけは!ということのみお伝えしたほうが良いかと思います。
- 話し終わるまで、さえぎらずに待ってほしいこと
- 緊張しなくていいよ、落ち着いて、ゆっくり言っての声かけはNG
我が子は小4の時点では、まだ緊張するタイプではなく、発表もじゃんじゃんできるタイプです。
ただこれは、また別の機会に話しますが、このようなタイプは少ないと思います^^;
緊張するお子さんも多いと思いますので、この場合は、可能であれば、上記に加えて
・音読や発表の順番を、本人の希望に応じて柔軟にしてもらえないか
といったことも相談してもいいかと思います。
実際、我が子も小2の参観日の発表で1度相談したことがあります。
もちろん対応が難しい場合もありますが、
可能であれば、その子が安心して学校生活を送るための「工夫」だと思うので
相談だけはしてもいいかもしれません。
また、これも経験したことですが、口頭だけだとイマイチ伝わらないこともありました。
先生と保護者、両者に時間が取れるのであれば、5分でも10分でも対面のお時間を頂戴し、
資料と一緒に説明すると効果的です。
私の場合は、自分で資料を作ったこともあります。ただ、初めはハードルが高いので
すでに作成してくださっている資料を使うこともありました。
実際に使用していた資料はコチラです。
【さいごに】親から始めるサポート
新しい先生にお願いごとをするのは少し勇気がいります。
でも、親が先に橋渡しをすることで、子どもも安心して学校でのびのび過ごせるようになります。
吃音があっても、自分らしく、前を向いて進めるように。
先生とのチームワークで、今年も一歩ずつ、歩いていけたらと思っています。


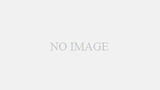
コメント